
カスタマーマーケティングとは?今注目されるカスタマーサクセスとの関係も解説

SaaS型ビジネスやサブスクリプション型ビジネスが増加するにつれ、カスタマーサクセスの重要性が叫ばれるようになりました。かつて、「CS」といえばカスタマーサポートの略として用いられることが一般的でしたが、今ではカスタマーサクセスを指す記号になりつつあります。
すでにカスタマーサクセス組織を立ち上げて運用している企業も少なくありませんが、これからカスタマーサクセスに取り組みたいと考える企業に一度立ち止まって考えていただきたいのが、自分たちのカスタマーサポートがカスタマーサクセスを実施できる土台として十分に機能しているか?という点です。
本記事では、カスタマーサクセスとカスタマーサポートを比較しながら、それぞれの役割や目標を紹介し、先に取り組むべきはカスタマーサポートのテコ入れなのか、それともカスタマーサクセスの立ち上げかについて検討します。
「カスタマーサクセス」とは、自社の製品・サービスを活用することで顧客の成果を追求し、アップセルやクロスセルを促したり解約を抑えたりしながら、LTV(Life Time Value/顧客生涯価値)の最大化を目指す活動や役割、組織のことです。
SaaS型ビジネスやサブスクリプション型ビジネスの増加とともに注目を浴びるようになった理由は、これらのビジネスでは利用期間中に毎月定額の売り上げが発生するため、顧客に成果を出し続けてもらうことで継続利用やアップセル・クロスセルを促す活動と相性が良いためです。逆に、活用できていない顧客を放置すれば、解約につながってしまいます。
「カスタマーサクセスとは」をわかりやすく解説
カスタマーサクセスが注目される理由、カスタマーサクセスの効果や実践する上で重要なことをご紹介しています。
カスタマーサクセスとカスタマーサポートは、顧客支援を行うという意味では似ていますが、実はミッションから機能、担当者に求められる役割まで、まったく異なる組織です。
| カスタマーサクセス | カスタマーサポート | |
| ミッション | 顧客の成功体験を作る | 顧客満足度の向上 |
| コミュニケーション | 能動的 | 受動的 |
| 機能 | 活用支援(オンボーディング) | 操作支援(ヘルプデスク) |
| 必要な能力 | 提案力、データ分析、進捗管理 | トラブルシュート、丁寧さ、スピード |
| 指標 | 売り上げ、解約率、ファン化 | 対応件数、解決数、満足度 |
次に、カスタマーサクセスとカスタマーサポート、それぞれのミッションと成果指標(KPI)について、詳しくご紹介します。
カスタマーサクセスのミッションは、「顧客の成功体験を作る」ことです。利用中の製品・サービスが「不要」と思われれば解約されてしまいますが、「役に立つ」「ビジネスに貢献している」などと感じてもらえれば、継続利用やアップセル・クロスセルの可能性も出てきます。
ただ、すべての顧客に対して一様の対応を行っていては、無駄が生じたり物足りなさを感じさせてしまったりと過不足が生じるため、手厚く対応すべき顧客とそうではない顧客では対応を分けると効率的です。そこで、想定されるLTVが高い順に「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3層に顧客を分け、それぞれ最適なレベルで対応することで全体のリソースのバランスを取ります。
3層のうちでもっとも高いLTVが見込める、いわゆる大口顧客への対応がハイタッチです。一般的に、顧客数は最も少なく、手厚いフォローが可能です。
ハンズオン(実習形式)によるオンボーディング(製品・サービス定着化のフォロー)や、個別の勉強会・ミーティングなどの開催、顧客の収益アップを実現するためのカスタマイズやオリジナルプランなどを提供します。
ハイタッチよりはLTVが低く、最下層のテックタッチよりも高いLTVが見込める顧客層への対応のことで、ハイタッチとテックタッチの中間くらいの手厚さでのフォローを行うことになります。
LTVに見合うようなグループでの集団対応が基本となり、ワークショップやセミナー、イベントの開催、トレーニングプログラムなどを提供します。
LTVがもっとも低い顧客層への対応のことで、費用対効果を考えると手厚いフォローは行えません。ただし、顧客数としては最も多く、電話やメール、Web会議システムといったICTや、マーケティングオートメーション(MA)、チャットボットといったツールを活用した対応が主流となります。
【関連記事】カスタマーサクセスにおいて必要不可欠 ~ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチ~
カスタマーサクセスの成果指標(KPI)の例は、以下の通りです。
【カスタマーサクセスの成果指標(KPI)例】
カスタマーサポート部門のミッションは、「顧客満足度の向上」です。
もう少し細かく見ていくと、オペレーターにとってのミッションは、「顧客に不満を残さないことと、顧客の声(VOC)の蓄積」で、スーパーバイザー(SV)などマネージャーのミッションは、「蓄積されたVOCを分析し、サービスそのものを改善できるよう、営業、開発、マーケティング、経営層などの必要な部門に声をかけ、サービス改善サイクルの起点を作ること」となります。
カスタマーサポート部門は、いわば「おもてなし」を行うチームです。そのような抽象的なミッションを達成できているか否かを測るカスタマーサポートの成果指標(KPI)の例は、KGIをどこに置くかによっても変わってきますが、以下のようになります。
【カスタマーサポートの成果指標(KPI)例】
次に、それぞれの成果指標(KPI)例について、具体的にどのように負うべきかについて解説します。
カスタマーサポートチーム全体での問題解決率です。「製品の機能として実現できない」といった物理的な内容を除き、基本的に100%を目指します。最も重視したいのはFCR(First Call Resolution/一次解決率)で、これを高めることはもちろん、健全であるかどうかのバロメーターにもなります。
解決までの時間が長いと顧客満足度は下がります。高いFCRとともに、顧客との往復数を下げ、解決時間を短縮することを目指します。
また、「どの製品・サービスに関する問い合わせの解決時間が長いのか?」といった分析を行うことで、改善施策にもつなげられます。
内容(要望なのか質問なのか、など)や、どんな製品・サービスについてのお問い合わせなのかを分類し、推移などを分析します。オペレーターでなくても解決できるもの質問については、FAQの充実化などで改善を図ります。
サポートの対応について顧客にアンケートを実施し、その調査結果の数値をKPIとします。
顧客からのコール数に対し、つながった率を目標値とします。想定されるコール数よりも、用意しているオペレーター数が極端に少ない場合などでは、そもそも顧客の動向を理解できていないため、改善が必要ということになります。
【関連記事】サポートセンターの歴史 ~カスタマーサポートの源流~
結論からいえば、カスタマーサクセスを立ち上げる前にまず、カスタマーサポートのテコ入れに注力すべきです。
理由は、「カスタマーサポートのミッション、成果指標(KPI)」でもお伝えしたように、カスタマーサポートの役割が、サービスとして当たり前の品質を提供することだからです。
顧客からのお問い合わせに回答できない、つまり顧客の課題を解決できない状態では、顧客の成功体験を実現することは到底できないでしょう。
また、カスタマーサポートは「企業の顔」であるとも言われます。受注後、一番長く顧客とコミュニケーションを取っていくのはカスタマーサポート部門だからです。もし、カスタマーサポートが万全ではなく顧客から信頼されていない状態では、いくらカスタマーサクセスを立ち上げて顧客に提案を行ったところで受け入れてもらえません。
カスタマーサクセスの立ち上げを検討しているなら、まずはカスタマーサポート部門のKPIを確認し、十分に機能しているかどうかをチェックしてから判断した方が良いでしょう。
カスタマーサポートのテコ入れが済み、自社として「当たり前」品質のサービスを提供できるようになったら、いよいよカスタマーサクセス組織を立ち上げることになります。
カスタマーサクセスがオンボーディングなどの活動を進めていくと、顧客は製品・サービスを積極的に利用し始めるため、不明点や疑問点も出てきます。その結果、カスタマーサポートへの問い合わせ数も増えていきます。
そのときにカスタマーサポートのサービス品質が低く、不満が残る結果となれば、せっかくのカスタマーサクセスが台無しになってしまいます。カスタマーサポート部門が全顧客に対して、満足度の高いサービスを提供し続けことが、カスタマーサクセスへ貢献することになるのです。
逆に、カスタマーサクセス部門は、不明点についての問い合わせ窓口がカスタマーサポートであることを顧客へしっかり認識させる使命があります。
カスタマーサポート部門を持っていない企業はほとんどないといって良いでしょう。カスタマーサポートを運営していく中で、さまざまな課題が出てきますが、カスタマーサクセスを立ち上げるためにも、カスタマーサポート部門における課題をまずは解決していきたいところです。ここでは、カスタマーサポート部門が抱えがちな課題と、それを解決するための方法をお伝えします。
カスタマーサポート部門に人員が増えていくと、それぞれの対応スキルの違いから対応速度や件数、品質に差が生まれてしまいます。
ITツールを導入して、オペレーターそれぞれの対応件数・対応案件(内容)を可視化することで、SVが案件を振る目安になり、ばらつきを抑えることができます。
難易度の高い内容や、件数の少ないサブ商材に関する問い合わせになってくると、社歴の長い人や経験のあるオペレーターでないと対応できないという課題もあります。
SVなどが問い合わせ全体を分類し、分析することで、オペレーターごとに偏りが見えてきます。その偏りを解消すべく、勉強会の開催や個別研修を実施しノウハウを共有しましょう。場合によっては、顧客向けFAQの充実化が必要になるかもしれません。これもITツールの導入で解決しやすくなります。
また、ツールによっては、オペレーターへの研修そのものを支援してくれる機能もあります。
営業部門など他部門経由で入ってくる問い合わせでは、顧客からヒアリングできている項目に抜けがあったり、曲解されていたりなど、コミュニケーションロスが発生しがちです。
また、他部門から、顧客への対応状況について聞かれ、それに回答することもコミュニケーションロスの一つです。
CRMなどのツールにそれぞれの部門が顧客への対応記録を残し参照できるようにすることで、コミュニケーションロスを減らせます。
いま、注目を浴びているカスタマーサクセスですが、立ち上げを検討しているならまずはカスタマーサポートのテコ入れからの着手をおすすめします。カスタマーサポートのサービス品質が悪ければ、カスタマーサクセスを運用しても結局は顧客満足度の低さからアップセルやクロスセル、利用継続は見込めないからです。
カスタマーサポートを運用する中で出てくるさまざまな課題の解決には、ITツールの導入が効果的なことが多いです。手作業で対応しきれない部分は、ツールを活用して効率よく顧客満足度を高めていきましょう。
サービス利用を開始した後の顧客との関係性において、サービス提供者が行うカスタマーサクセス活動や考え方がどういったものかを、できるだけわかりやすく解説しています。
ヘルプデスクの問題点から、解決策としてのサービスデスクをいかに構築するか、そのステップをご紹介します。ヘルプデスクの事例集もあわせてダウンロードいただけます。
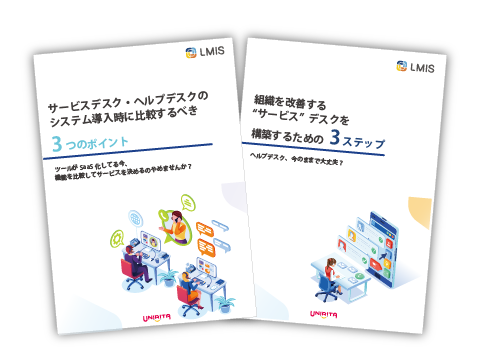
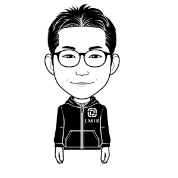
執筆者情報:
澤田 大輔(さわだ だいすけ)
株式会社ユニリタ
クラウドサービス事業本部 ITマネジメントイノベーション部
サービスマーケティンググループ
IT部門におけるITILの活用だけでなく、ITを基盤としているサービスにおいてのITILの活用、その先にある顧客満足度の向上のためのプロセスモデルを発信しています。
愛犬(チワワ)と愛娘と一緒に遊ぶのが日課です。
Rankingランキング
New arrival新着
Keywordキーワード