
製造業が自社製品を直接売るには?DXを実現しお客様に選ばれるECサイトを構築しましょう

前回の記事では、働く環境が多様化する中で、チームワークの重要性についてまとめてみました。
テレワークが導入され、働く場所が多様化している企業も増えているかと思いますが、そのような環境下でチームワークを強化するためには、実際に何から始めたらいいのでしょうか?仕組みだけ取り入れても行動を変えていかないと本質は変わりません。
本記事では、チームワークを強化するための第一歩として、オープンな場をつくることの重要性についてご紹介します。
テレワーク環境における職場の課題としてあげられるものとして、コミュニケーションの場が少ないというのがあります。テレワークを実施している企業では、メンバー間のコミュニケーションの場が減少することによる組織力の低下が、よく課題としてあげられます。
パーソル総合研究所の「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」によると、「組織の一体感」について、テレワーク実施者のうち36.4%が、テレワーク実施後に組織の一体感が低まったと回答しています。[注1]
働く場所がお互いに離れていくと、例えば上司の考えが理解できない、同僚が何をやっているかわからない、チームメンバーとの連携がうまくできないなどの悩みが増え、メンタル面でも働きがいが薄れていくことも多いのではないでしょうか。
Webミーティングで毎日顔を合わせているから大丈夫、と管理職側は思うかもしれませんが、ミーティングの内容を振り返ってみて本当にそうでしょうか?
指示をするだけのミーティングになっている、ミーティングが多くて仕事をする時間がとれない、自分には関係ないミーティングでも参加しないとよくわからなくなる、そのような内容になっていないでしょうか?
ただ連絡事項を通達するだけや、作業を指示するだけのミーティングばかりになると、目の前の仕事を処理するだけで思考が止まってしまい、チームとしてのビジョンやチーム全体を成長させる意識が薄まり、単純にルーティンワークを実施するだけのチームになってしまいます。
以下のような状況が起きていないでしょうか?
進捗会議や仕事を割り振るだけのミーティングではメンバーが苦痛を感じ、計画通りに自分の仕事ができてなかったとしても、「頑張ります」「やります」としか言えない状況となってしまいます。「実は困ってます」と切り出せない空気感があり、ちゃんと伝えきれない悩みがあったりします。急に発生する突発的な仕事、顧客からの問い合わせ対応、スケジュール変更による調整など、計画通りに進まないことは日常的に起きます。その中で仕事も増え続けるとますます悩みごとが多くなり、ヘルプを発信したいが伝える場がなくて抱え込んでしまいます。
管理職側としても、業務課題への対応、上位職からの突発的な指示への対応があり日々忙しいかと思います。自分では解決できないので部下に仕事を割り振るとしても、ただ上からの指示をそのままチームメンバーに丸投げしてしまうと、タスク志向となり協働した環境がつくれないという問題が起きます。アドバイスしようにも、管理職自身が本質を自身が理解できていないと伝えることすらできません。スタート時は共有できていたことが、状況や時間経過により変化するため、相談しあえる場がないと、段々と認識のずれが生じてきます。
情報共有や伝達のために多くの時間を費やしているが、仕事の情報のみ共有し、認識をあわせないことが問題です。双方向の会話から個々が共感、理解することを積み重ねることでコミュニケーションは成立しますので、単純な共有事項を伝えるのではなくて、共感するための議論をする場をつくることが重要となります。
集まって議論を何度も実施して、本質を深くつくように進めることで、結果として新しいアイデアや、いろいろな仕事の工夫を生み出すための効果的な方法があります。「ワイワイガヤガヤ」自由に意見を出し合うという「ワイガヤ」の手法です。
基本的には、「課題やテーマを共有しながら、自由に話し合い、深いところにある答えを探り出していく」という流れです。[注2]
管理手法やツールをただ導入してもうまくはいきません。ちょっとした相談ごと、たった今起きている問題への対応は、メンバー間でワイワイガヤガヤすることで解決することも多いです。そういった場があるからチームが強化されます。
ビジョンを語るのも良いですが自己満足で終わるのではなく、現実レベルでの共感が重要であることを理解し、おのおのの現状から考えや疑問をメンバー間に共有することを促進するようにします。お互い共感できれば、チームが一体となって活動ができるようになります。コミュニケーションを活性化させ、知恵を結集させて解決策を生み出すだけにとどまらず、参加したメンバーの意思疎通が図れるようになり、ミーティング以外の時間でも良好なコミュニケーションがとれるようになります。そして、チームの垣根を越えた協力者も現れると、オープンイノベーションを巻き起こすことにもつながります。
チームの風通しが悪いと、やっていることがよくわからず、方向性がバラバラとなり一緒に活動している気がしないでやらされ感でいっぱいとなります。
お互いの仕事を知り、そしてなによりも人となりを知り人間関係をつくりましょう。そのためにはチームの一人ひとりの業務をばらしていく作業が意味を持ち、見える化ができていきます。仕事や置かれた状況がお互いに見えるようになり、そこから協力する意欲がわいてきます。その結果、仕事に取り組む姿勢をしっかり持とうという動きになります。
チームには向かうべき目標があります。目標を達成するためには、最大の力を引き出せるチームでなければなりません。リーダーは、メンバーが自発的に考えて、主体性をもって動くチームを作ることを目指しましょう。いくら個人の能力が高くても、一人では大きな成果を出すことは困難です。目標に対して意識をもって自分なりの考えをまとめ、他のメンバーと協力しながら進められるようになるといった関係をどう作り上げるかがリーダーには求められます。
目標は成し遂げようとするチームのゴールです。あるべき方向性を明示的に示したゴールです。コミュニケーションの場ができたら、次にゴールを目指して、一人ひとりが最大限の力を発揮しながら、協力できるチームを目指すために、まずはビジョンを明確にして共有していきましょう。
しかし単純に一方通行で共有しただけではだめで、共感を得られるような説得性をもった内容で伝えないと意味がありません。上からのメッセージをそのまま伝えるのではなく、リーダー自身が内容を理解して、明確なメッセージを伝えられるようにしましょう。
前述のとおり、まずなんでも相談できる雰囲気づくりと継続できる環境づくりからはじめます。そしてそのあと、職場で働く一人ひとりの仕事の内容や、自分のことを素直に話せるようになる場を形成していきます。
その後、やったことの振り返りをして、各メンバーがやれなかったことを反省するとともに、仕事の進捗を妨げる問題点をあげて、解決策を検討することで計画力を向上させます。
計画力を向上させることでコミュニケーションが活性化し、潜在する問題を察知し、早めに対処を行い、効果的なOJT(On the Job Training)ができるようになるなど、マネジメント力が向上してきます。
コミュニケーション力、計画力、マネジメント力の向上は、個人とチームを同時に成長させて、目標達成ができるチームをつくりやすくなります。これは短期的にはできないことで、長期的に根付いて自然とできるように根気よく啓発していくことが大事です。
将来にむかって大きくビジョンを描くことを狙い、現状の課題を解決し、チームの将来を考えていきましょう。そうなると、理想像に向けてチーム内で本音で語りあえるようになります。
皆さん、いかがでしたでしょうか? 当てはまる課題がありましたら、チームワークの理想を考えてみて、まずはオープンな場を形成するところから行動してはどうでしょうか。
オープンな場をつくり、チームの方針をメンバーが腹落ちした後は、具体的に計画をたてることを進めていきましょう。自分の仕事は自分で計画し、セルフマネジメントで調整することが重要です。次回は業務の総量をばらして計画立案をする流れについて説明していきます。
[注1]パーソル総合研究所 新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査調査結果
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/research/assets/telework.pdf
[注2]ビジネス+IT 「ホンダ流ワイガヤ」実践のコツと方法を、元ホンダ 本間 日義氏にインタビュー
https://www.sbbit.jp/article/cont1/32161
「Serccs Board(サークスボード)」は、チーム全員の仕事を見える化することにより、チームの目標達成に向けて生産性を高めることができるタスク管理ツールです。
チームメンバーの1週間の予定をカレンダーで可視化し、メンバーの負荷状況を把握してチームで協力し合えます。プロジェクトを管理できる機能やGoogleカレンダーとの連携も可能です。
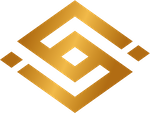
執筆者情報:
ユニリタ Serccs Board チーム
株式会社ユニリタ ビジネスイノベーション部
チームタスク管理ツール「Serccs Board」のプロモーション担当チームです。
職場におけるチームの知的生産性の向上に注力してきたメンバーが、チームワークに課題をお持ちの方に役立つタスク管理術やツールを活用した解決策を発信していきます。
Rankingランキング
New arrival新着
Keywordキーワード