
いま電子帳簿保存法を検討すべき3つの理由

前回はサブスクリプションサービスの概要と代表的なサービスについてご紹介しました。
今回は、みなさんが意外と知らずに利用しているかもしれない身近なサブスクリプションサービスと、その成功事例などを紹介します。
企業側がプッシュしたいコンテンツをオススメ=レコメンドすることでサービス品質の向上を図り、顧客満足度を高めて解約を低減するサブスクリプションサービスがあります。
レコメンドとは、普段使う定食屋に置き換えるとわかりやすいと思います。飲食店では「日替わり定食」や「店長のオススメ」といったメニューを、余剰食材をレコメンドという形で顧客に提供しているケースがほとんどです。
日替わり定食などはボリュームのわりに良心的な価格設定で顧客側の満足度も高いメニューが多いですが、企業側は余剰食品を捌いて食品ロスを低減する目的があります。余剰食品をただの値引きで販売してしまうとコンテンツの利率が低くなり定常化も厳しいですが、「オススメ」というレコメンドの形で提示すれば利率を落とことなく販売可能です。
提供されたコンテンツが望んでいたモノと異なった場合でも、顧客は「自分の偏好では選択しないモノを選んでくれた」という点をメリットとして納得してくれるケースがあります。

以前のサブスクリプションサービスではプロダクトを利用しなくても利用料を収めてくれる顧客を歓迎する見方がありましたが、今後は顧客のニーズを満たすコンテンツを提示して利用率を高める取り組みが重要です。
2018年10月時点で総加入者数が1億3,000万人を超える大手映像系ストリーミングサービスが発表したアルゴリズムによると、月あたりの利用頻度が一定水準を下回るユーザーは解約率が急激に高くなると示されていました。
同映像系ストリーミングサービスは顧客の利用率低下を防ぐために、ユーザーの視聴履歴や検索キーワードから類似性を分析し、ユーザーが好みそうなコンテンツをピックアップしてオススメするレコメンドサービスを行っています。レコメンドによって利用率の向上を図る取り組みの結果、ユーザーの総視聴タイムにおける7割以上がレコメンド経由になりました。レコメンドはカスタマーサクセスにリーチできるアプローチの一つであり、精度を高めて顧客の偏好に近しいオススメを提示できれば利用率を高めて顧客の解約を抑えられます。
サブクリプションサービスには非IT型のサブスクリプションサービスもあります。この場合、商品やサービスの利用者数が鍵であり、一般的に購入(利用)頻度が低くすぎるプロダクトは相応しくありません。目立った競合が存在しない分野のビジネスをサブスクリプション化して良質なプロダクトを提供すれば、その市場における大多数の利用者を顧客化できる余地があります。
非IT型のサブスクリプションサービスは、昔からある例をあげると新聞の定期購読などがあります。新聞はビジネスパーソンにとって1日の世界動向やトピックスを知るために必要であり、常に情報収集ツールとしてのニーズがありました。しかしスマホやタブレット端末の普及によってコンテンツがオンライン化され、各メデイアは電子版にシフトしつつあります。メデイアが変遷しても情報収集のニーズはなくならないため、新聞(電子版)はサブスクリプションサービスとして長く機能しているのです。
既存のビジネスをサブスクリプション化している企業も多くあります。
株式会社TesTee(テスティー)では、20代の男女1.217名(男性600名、女性617名)を対象に実施。オフラインのサブスクリプションサービスとして利用してみたいものとして以下のような結果が出ています。[注1]
|
男性 |
女性 |
|
1位.フード系 |
1位.美容・コスメ |
|
2位.車・自動車 |
2位.フード系 |
|
3位.美容・コスメ |
3位.ファッション系 |
男女ともに、フード系、美容・コスメ系のサブスクリプションサービスを利用したいと考えている人が多いようです。
ここでは、既存のビジネスをサブスクリプション化して企業・顧客にメリットが生まれた例を3つ紹介します。
[注1] 【ミレニアル世代対象】サブスクリプションサービスに関する調査 | TesTee Lab(テスティーラボ)| 若年層(10代、20代)を調査するアンケートメディア
飲食店における余剰食品を使ったメニューを顧客に提供し、集客と追加注文を促すサブスクリプションサービスが存在します。利用者(顧客)は月額料をはらうことで、同サービス加盟店から提供される余剰食品を使ったメニューを1日1品無料で食べられるというサービスを受けられます。
このサブスクリプションサービスで重要になるのは、ユーザーのニーズと余剰在庫のマッチングです。この2つのバランスが保たれていないと、このサービスは成り立ちません。そのため在庫管理システムといった他のツールを活用する必要があります。

月ごとに様々な化粧品を試したいという顧客のニーズに応え、コスメを毎月顧客の自宅に届けて使ってもらうサブスクリプションサービスがあります。サービス利用者は定額の費用を毎月収めることで、毎月贈られてくるトレンドなメイクアップアイテムやケアアイテムを試すことが可能です。ただし月額費用や梱包されているコスメの数量、ブランドの傾向といった内容はサービスによって異なります。
贈られるコスメはユーザーが選んだアイテムではなくメーカー側がレコメンドしたアイテムであり、オススメしたいコスメを顧客に使ってもらえます。普段自分の好みでは試さないアイテムに挑戦できるため美容意識が高く流行に敏感なユーザーから注目されています。

子どもに知育玩具を買い与えて遊ばせたい一方で、「どの知育玩具を選べばいいかわからない」や「飽きると保管場所が圧迫される」といった悩みを抱える消費者が多いとされています。知育玩具における消費者の悩みを解決するため、子どもに飽きられにくい最適な知育玩具をレコメンドし、保管場所の圧迫や廃棄といったロスを低減するサブスクリプションサービスが注目されています。
同ビジネスは子どもの歳や性別、顧客満足度調査といったデータからプランナーが最適な知育玩具を複数選んで顧客にパッケージングするサービスです。
月額制で顧客を獲得するサブスクリプションはビジネスにおいて以前から取り入れられていたモデルですが、登場してから間もない黎明期はソフトウェアなどのデジタルな分野に限られていました。しかし昨今は消費者(顧客)の意識が価値を所有せずに利用する方向へシフトしており、ビジネスのサブスクリプション化が急速に広がりつつあります。そのため将来的にはサブスクリプションがビジネスモデルにおける標準となるかもしれません。
インターネットの普及によって情報収集が簡易となった昨今、革新的な商品やサービスの情報はメデイアを通じてすぐに拡散します。普遍的に一定水準の情報収集ができるようになった一方で、ビジネス面ではあらゆる市場が均衡化して競合との差別化が困難になりました。情報の可視化によって、サブスクリプションサービスはメジャーなビジネスモデルとなりつつあるのです。メデイアのオンライン化をごく自然に受け入れながら育ってきたミレニアム世代が労働人口の多くを形成する今後は、さらに王道的なビジネスモデルとなるでしょう。
次回は、サブスクリプションサービスで重要な「カスタマーサービス」についてご紹介します。
サブスクリプションサービスのBtoC、BtoBにおけるサービス例やレベルについて解説。そして、BtoBでの主流であるSaaSにおけるカスタマーサクセスに重要な3つのポイントをご紹介します。
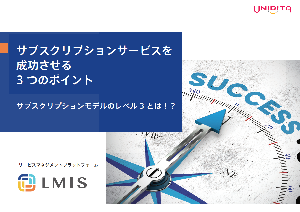
Rankingランキング
New arrival新着
Keywordキーワード