
ヘルプデスクとは? ヘルプデスクを効率的に行うツールをご紹介
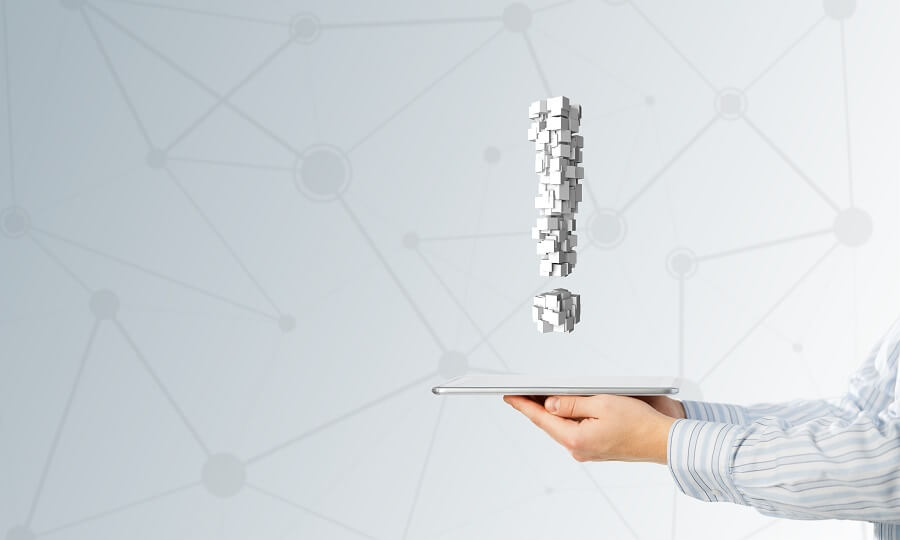
2015年、2016年と2年連続でベストセラーになっていた『嫌われる勇気』という本を読みました。
内容としてはアドラーという人が提唱している心理学の説明をしている本で目的論という観点が面白かったです。
目次としては以下のようになっています。
第1夜 トラウマを否定せよ
第2夜 すべての悩みは対人関係
第3夜 他者の課題を切り捨てる
第4夜 世界の中心はどこにあるか
アドラー心理学では他の心理学の原因論とは違い目的論というのを取っています。
問題を抱えているシステム運用の現場での例で考えてみると、原因論は「いまシステムが安定稼働していないのは昔からあるアプリケーションの仕様がよくないからだ。それでも現状で何とか回してやっているんだ!」というように原因を過去に求める形になります。
しかしアドラー心理学的に言うと「システムがうまく回っていないことで得られる何か都合のいいことがある」という風に考え、その理由づけとして過去の事象を話しているに過ぎないということになります。
例えば「システムがトラブル頻発で忙しい」という状態を維持することで、職場内での自分の役割を維持させようとしているという風に見ることが出来ます。
つまりアドラー心理学の観点から見た場合、このシステム管理者は「問題がある状態を望んでいる」ということです。
現場の人が改善に意欲を見せないときは、その人が現状を維持することで何か利益を得ていると言えるでしょう。
ITサービスマネージャの立場で運用現場を改善したいときに、この人をどうするかということを余り考えすぎない方がよいです。
面談などを実施して新しい役割を用意したりなどは管理者の仕事としては実施すべきだとは思いますが、その人がどういう働き方をするのかは最終的には当事者の問題でありITサービスマネージャーの人がどうこう出来る話ではないということです。
また目的論に立った時、ITサービスマネージャーは「どうしてこうなんだ」という分析よりも「どうなりたい」かということを考えることが重要になります。
※目的を達成するための分析は必要だと思いますが、出来ない理由探しとしての分析には意味はないということです。
会社で働いていると査定というのがあったりして、それを上げていくことが良いことだと思いがちです。しかしそれは他者のものさしで生きていくことになり、他者の人生を生きるということになります。
運用の改善を行うとして、現場の担当者の人の期待を満たすために動いていたら、ITサービスマネージャーの人が思い描く運用は実現できないかもしれません。
現場担当者を配慮して動いたとしても、現場担当者が好きになってくれるかどうかはわかりません。
改善を進めて行った結果、ITサービスマネージャーの人がどう思われるかは「自分の課題」ではなく「他者の課題」です。
結果として嫌われることになろうとも、ITサービスマネージャーの人は「システム運用をどうしたい」という目的に向かって進んでいくべきです。
そのためにITサービスマネージャー(のみならずリーダー的な立場の人間すべて)は「どうしたい」という考えをしっかりと持つ必要があるでしょう。
ただしアドラーは好き勝手にやれということを言っている訳ではなく、社会のために生きるのが幸福につながるという話もしています。
全てをお伝えするのは難しいので、後は本を読んでみてください。
Rankingランキング
New arrival新着
Keywordキーワード