
ビジネスを飛躍させるデータドリブンの力
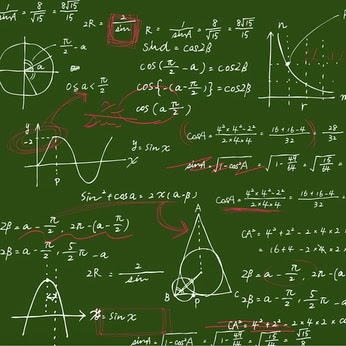
ちょうど私立大学の入試が一通り終わり、大半の受験生は進路が見えてきた時期。
国公立大学も前記日程試験が終了し、国公立大学進学志望の方々は合格発表を前に緊張の最中にいる時期だと思います。
筆者は昔、高校生指導の塾講師をしていたこともあり、毎年この時期は何故か私もそわそわしてしまいます。
よく合格発表というと、大学に設置された大きな掲示板を前に受験票を握りしめて
(あるかな・・・、あるかな・・・?)
みたいな絵が思い浮かぶと思いますが、少なくとも私が受験した10年前の段階で、合格発表はWebがメインでした。受験番号を入力して[次へ]ボタンをクリックすると、画面がパッと切り替わり一瞬で合否が表示されます。
その呆気なさときたら、もう、ね。
一応、大学にも合否発表の掲示板は設置されていますが、あんなのはもう合格者が記念撮影するためのオプションでしかない訳です(暴言)。
私のときは、まだあまり一般的ではありませんでしたが、今の子たちだったらまずSNSにアップするでしょうから、進路が決まってない側からすると絶望感は凄まじいでしょうね。
いやいや、そもそも受験勉強の最中にSNSなんかやっちゃダメですよ。開いたら負けですよ。
ところで昨年、2020年からセンター試験が大幅に見直される、というニュースが報道されました。
センター試験 2020年度から複数回に 「一発勝負」避ける
見直し案の内容を簡単にまとめると、
応用力と聞いて真っ先に思い浮かんだのが、塾講師を務めていたころに出くわした、ある年の東大入試の数学の問題(調べてみたところ、2003年・理科系前期とのこと)。
「円周率が3.05より大きいことを証明せよ」
このシンプルさ。このインパクト。
一番有名な解法としては、(円周)>(円に内接する正八角形or正十二角形の外周)を三角比やら三角関数を使ってちくちく計算するだけ。思いついてしまえば何ともないものですが、マーク式の問題では、なかなかこのような応用力というか発想力を測れないのも事実です(極端な例かもしれませんが)。
ただ、従来のマーク式でも色々問題(※)が取り沙汰されていましたが、記述・論述形式になることで別の問題が山積みになることは目に見えています(採点どうするんだ?とか)。
良い・悪いについては様子見といったところだと思います。
運用についてコンピュータの技術進歩次第、というのがなかなか興味深いところです。
教育現場におけるデータ活用として、最近ではよく「アダプティブラーニング(Adaptive Learning)」という取り組みが挙げられます。
生徒一人ひとりの学力(理解度)を鑑みて、当人にとって最適な学習プランを履修させるというもの。
この考え自体は結構前々からあって、それこそ私が塾講師を務めていたころから、従来の対面式の授業だけではなく、単元毎に選んで受講できるオンデマンド授業(映像授業etc.)も実施されています。
「いつやるの?今でしょ?!」の林修先生が有名になった東進ハイスクールさんは、かなり前から映像授業に特化されています。
数年前、映像授業を家庭のPCからも受講できるようにする、なんて話があった際は、各家庭のPC・インターネット普及状況によって不公平さが生じるため、なかなか踏み切れない課題もありましたが、今ではタブレットを生徒全員に配布なんてことも。
すごい時代になったもんですね。
http://edtech-media.com/2014/01/15/eikou-ipadmini/
最近、個別指導型の塾・予備校のテレビCM露出が増えてきていますが、個別指導というのもいわばアダプティブラーニングの一つ。その生徒の理解度に合わせた授業を、講師側がコントロールして展開するものです。
これらのアダプティブラーニングにビッグデータのエッセンスを加え、各自の学習理解度をより精密に計る(測る)ことで、生徒一人ひとりが、より自分に適したプランで勉強することが出来るようになります。
今は単元毎の理解度管理等が主ですが、将来的には、
その生徒が集中できる環境は?とか
脳が活性化されている時間は?とか
シチュエーション的な要素も含めてプランニングできるようになるのかもしれません。
一方で、上記のような入試形態の見直し等で、従来の進学校・塾・予備校が持っている「受験テクニック」が通用しなくなる可能性もあり、今教育現場で推し進められているビッグデータ活用も大幅な方向転換をするのかもしれません。
どうなるんだ教育格差問題。
今後も教育現場におけるデータ活用については注目していきたいところです。
※余談ですが、よしもとばななさん著の「TUGUMI」がセンター試験の現代文の問題として出題されたとき、よしもとさん自身が解いてみたら半分も点数を取れなかったエピソードは有名ですね。ただ、下記URLのコラムを読む感じだと、問題として使われることについては、好意的に受け止めているようです。
http://www.asahi.com/edu/center-exam/lookback/ASF0TKY201312260397.html
Rankingランキング
New arrival新着
Keywordキーワード